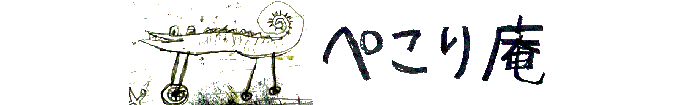20160117
受験シーズンになると思い出す、大家さんのこと。
札幌の貧乏アパートの、陽のまったく当たらない一室に住みつき、毎日深夜にタクシー洗車のバイトに出かけて朝帰ってくる生活をしていたころのこと。そのころ、自分が受験勉強していることを誰かに話したのは、バイト先の先輩Nさんに巧妙に誘導尋問されたとき一度きりだったはずなのだが。
大学の二次試験当日の朝。ぼくはいつものようにバイトから帰ってきた。冬の現場は寒いからがむしゃらに体を動かさざるを得ず、とても疲れていた。アパートの入口の共同玄関で靴を脱いでいると、ぼくを呼び止める大家さんの声がする。大家さんは年配の女性で、娘らしい女性と二人で玄関に一番近い部屋に住んでいる。今月の家賃を払い忘れたっけ?と思って一瞬ぎくりとしたが、どうもそういう用件ではないようで、「これ、今日持って行きなさい」といって、彼女はぼくに包みを差し出した。ぼくは事情を飲み込めずにぽかんとして、何から質問すればいいのか考えあぐねた。けれど、彼女はそんなぼくにかまわず「がんばりなさいよ」というような一言を残してすぐに部屋にひっこみ、ぴしゃりと扉を閉めてしまった。
部屋に戻って包みを開けてみて驚いた。まるでおせち料理のような、かなり豪華な手作り弁当だった。受験しに行くなら昼食が必要だということにそのとき初めて思い至った。ぼくはなぜ大家さんが受験のことを知っているのか首をかしげながらも彼女の厚意に感謝して、その弁当をかばんに入れた。(蛇足ながらーーー昼になって包みを広げたとき、深刻な問題に気がついた。箸を忘れたのである。世間的な知識や生きる力に乏しいぼくは、この弁当を今ここで食べる手段をついに思いつくことができなかった。交通費以外の余分な現金は持っていないから何かを買いに出ることもできず、激しい空腹をかかえたまま試験を終えたのを覚えている。)
不思議はさらに続いた。
その後、合格通知が届いた日か、その翌日だったか。試験結果のことなどアパートの誰とも話したことはないにもかかわらず、再び大家さんに呼び止められ、「おめでとう」といって包装紙に包まれた箱を渡された。またも不意を突かれたぼくはうろたえて、「ああどうも…」というようなあいまいな応答をしたように思う。そのときの大家さんは、前回のようにすぐにぴしゃりと扉を閉めたりはせずに、たぶん「よかったわねぇ」とか「これから楽しみねぇ」とかいう賛辞の言葉をいくつもかけてくれたはずである。でもぼくは、そういう一般的な人づきあいの技術や感覚をまったく知らないから、「どうもすいません」などといった頓珍漢な言葉をぶっきらぼうにつぶやくことしかできなかった。もちろん、前回の弁当の感想や謝辞を述べることなど思いつきもしなかった。
ちなみに箱の中身は5足か10足くらいの靴下のセットで、在学中はもちろん、卒業してからもずいぶん長いことお世話になった。
当時のこのアパートは、「アパート」というより「長屋」といったほうが実態に近い。風呂なし。玄関とトイレは共同、玄関を入るとすぐに全入居者の下駄箱が並んでいる。その先の狭い廊下の両側に粗末な板扉を隔てて六畳一間の部屋がずらっと並ぶ。電話は玄関の隣、大家さんの住む部屋の前に一台だけ。外から電話がかかってくると大家さんが出て、大声で「誰々さ〜ん電話ですよ」と呼ぶ。名前を呼ばれた住人は廊下に出て行って受話器を取る。電話をかける人は10円玉をたくさん持って、話し終わるまで一定の間隔で10円玉を投入し続ける。郵便物は玄関に全入居者分がまとめてどさっと置かれ、大家さんが仕分けをして各人の下駄箱に放り込む。貧困層向けのこうしたシステムのアパートはこのあたり一帯ではごく普通のものだ。上下左右の部屋の会話や物音は筒抜け、断熱も全く期待できない。
いま思えば、こういうプライバシーのない環境だから、大家さんはぼくが受験の申込みや手続きで郵便や電話を利用するのを見聞きして、それで受験のことを知ったのかもしれない。
それにしても、人並みに挨拶もできない小僧が毎日深夜に出て行って朝帰ってくる姿は大家さんにどう映っていたのだろう。受験生のくせになぜ夜中に出歩くのか、親兄弟はどうしたのか、どこから来たのか、などなど問いただしたい不審な点がたくさんあっただろうに、ぼくには立ち入った質問はただの一度もしてこなかった。
バイト先でぼくをかわいがってくれた先輩のNさんとともに、ひとに感謝したいと初めて思った、そして感謝の念を伝えられなかった、忘れられないひとりである。